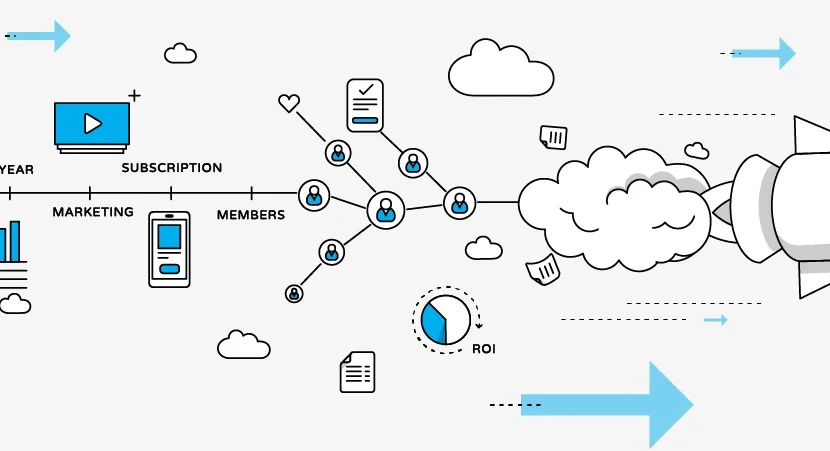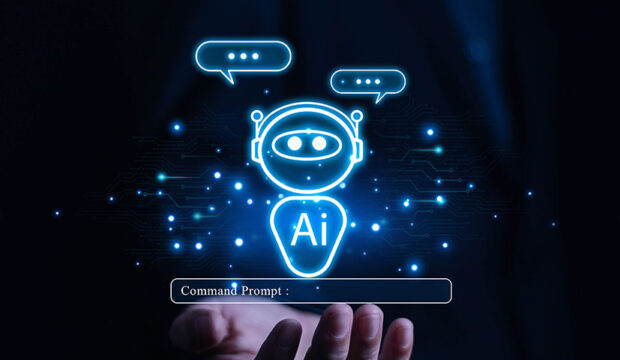「二重整形や豊胸術の、綺麗なビフォーアフター写真をホームページやインスタで紹介したい」
「海外から取り寄せた、最新の美容製剤や医療機器をメニュー化して集客したい」
でも、厚生労働省の医療広告ガイドラインで禁止されているらしい…。どうしたらいいの?
美容クリニックのウェブサイトで情報発信を行う際、こうしたお悩みをお持ちの担当者様は非常に多いのではないでしょうか。医療広告ガイドラインの厳しい規制により、クリニックの魅力や症例を思うように伝えられず、もどかしい思いをされているかもしれません。
しかし、特定の条件を満たせば、それら広告表現は認められるのです。
実は、医療広告ガイドラインには、特定の要件を満たすことで、原則禁止されている広告表現が可能になる「例外的なルール」が存在します。その鍵こそが、今回解説する「限定解除」です。
この記事では、医療広告ガイドラインの基本から、限定解除の具体的な条件、実践的なウェブサイトの作り方までを網羅的に解説します。ルールを正しく理解し、貴院の魅力を最大限に伝える武器としてご活用ください。
【この記事の目次】
1. 医療広告ガイドラインの基本:なぜ厳しいルールがあるのか
まず、そもそもの大前提である「医療広告ガイドライン」について簡単におさらいしましょう。
これは、不適切な医療広告によって、患者が誤った選択をして不利益を被ることがないよう、厚生労働省が定めた公的なルールです。このガイドラインの目的は、ひとえに「患者を守る」ことにあります。
美容医療に関する消費者相談は年々増え続けており、たとえば「広告に記載されいる料金と違った」「副作用やリスクの説明がなかった」「火傷をした」「国内未承認のよくわからない製剤を使われた」といったトラブルが多くみられます。これらトラブルを減らすために医療広告ガイドラインが作られたのです。
そのため、ウェブサイトやSNS(instagram、xなど)を含め、患者を誘引する可能性のある媒体では、原則として以下のような広告表現が「禁止」されています。
【原則禁止】されている広告表現の例
- 治療効果を保証したり、誇張したりする表現(例:「絶対にたるまないリフトアップ」「1回で永久にツルツル」)
- 手術前後の写真(ビフォーアフター写真)の掲載(例:二重整形、脂肪吸引、シミ取り)
- 国内で承認されていない医薬品・医療機器に関する広告(例:海外製の肌育系製剤、痩身マシン、ハイフ)
- 患者個人の体験談や口コミの紹介
- 著名人が利用しているかのような表現
2.広告の壁を突破する「限定解除」とは
前述の通り、多くの魅力的な表現が「禁止」されています。しかし、これらの禁止事項には、広告の“限定”を“解除”できる例外的な仕組みがあります。それが「限定解除」です。
テレビCMのように一方的に流れてくる広告と違い、患者が自らの意思で情報を探しに訪れるウェブサイトは、「情報提供の場」としての側面が強いと見なされます。そのため、「患者にとって有益な情報提供の環境」がきちんと整備されていれば、より詳細な情報(原則禁止されている事項を含む)を発信しても良い、とされているのです。
つまり限定解除とは、単なる規制緩和ではなく、「誠実で十分な情報を提供するなら、表現の幅を広げます」という、医療広告ガイドラインが示す一つの指針なのです。
3. 限定解除の必須条件【大前提+4つのキーポイント】
それでは、限定解除を適用するためにクリアすべき必須条件を、一つずつ見ていきましょう。これらはパズルのピースのようなもので、一つでも欠けていると限定解除は成立しません。
【大前提】患者が自ら見る「ウェブサイト」であること
まず最も重要な前提として、限定解除は、患者様がご自身の意思で情報を探しに来るウェブサイトや、インスタグラムやXといったSNS、LINEのメッセージ配信などが対象です。テレビCMや新聞・雑誌広告、看板、チラシなど、医療機関側から一方的に情報を送る媒体では、限定解除は適用されません。
この大前提を満たした上で、さらに以下の4つの条件をすべてクリアする必要があります。
3-1.【条件1】問い合わせ先の明記
医療機関の電話番号や問い合わせフォームなど、患者さんが容易に連絡できる問い合わせ先を分かりやすく記載する必要があります。
3-2.【条件2】自由診療に関する通常必要な情報の明記
保険適用外の自由診療について広告をする際には、以下の情報を併記する必要があります。特にリスクや副作用の記載は重要です。
- 通常必要とされる治療の内容
- 標準的な治療の費用(例:「脂肪吸引(大腿部) 〇〇円~〇〇円」)
- 標準的な治療の期間や回数(例:「医療脱毛 全5回コース」)
- 治療によって生じうる主なリスクや副作用(例:美容外科の豊胸術であれば術後のダウンタイムや被膜拘縮のリスク、美容皮膚科のレーザー治療であれば施術後の火傷や色素沈着のリスクなどが該当します。)
これらの情報は、限定解除を適用したい治療法(例:ビフォーアフター写真を掲載した施術)と関連付けて、同じページ内に分かりやすく記載する必要があります。
3-3.【条件3】未承認医薬品・医療機器に関する情報明記
国内で承認されていない医薬品や医療機器を用いた治療を広告する場合、以下の情報を明記しなければなりません。(例:韓国で話題の新しい美肌製剤や、国内未承認の美容医療機器などがこれにあたります。)
- 国内未承認であること
- 入手経路(例:医師等の個人輸入による)
- 国内に同一成分・同一性能の承認薬・承認機器があるか否か
- 諸外国における安全性等に係る情報(例:FDA承認)
3-4.【条件4】上記すべてを満たすこと
繰り返しになりますが、限定解除を適用したい情報(例:ビフォーアフター写真)が掲載されているページには、関連する必要情報がすべて記載されている必要があります。
4.【実践編】OK例・NG例で見る限定解除
理屈は分かっても、実際のウェブサイトでどう表現すれば良いか、イメージしにくいかもしれません。美容クリニックで特にニーズの高い施術を例に、OK・NGで比較してみましょう。
事例①:美容外科のビフォーアフター写真(二重整形)
❌ NG例
二重になった目元の写真と「パッチリ二重で人生が変わる!」といったメリットのみを掲載。費用やリスクが書かれておらず、患者に誤解を与えかねません。
✅ OK例
写真のすぐ近くに、以下の必須情報が分かりやすく記載されている。
- 施術名:二重埋没法(2点留め)
- 施術の説明:医療用の糸でまぶたを留め、二重のラインを形成します。
- 費用:165,000円(税込)
- 副作用/リスク:術後の腫れ、内出血、左右差、糸が取れる可能性など。
事例②:美容皮膚科の症例写真(シミ取りレーザー)
❌ NG例
シミが消えた肌の写真と「シミひとつない、生まれたての肌へ!」というキャッチコピーだけを掲載。治療費やダウンタイムの説明がありません。
✅ OK例
写真のすぐ近くに、以下の必須情報が分かりやすく記載されている。
- 施術名:ピコスポット(シミ取り放題プラン)
- 施術の説明:ピコ秒レーザーで衝撃波を与え、メラニン色素を細かく破壊します。
- 費用:88,000円(税込)
- 副作用/リスク:施術後の赤み、炎症後色素沈着、稀に白斑化の可能性など。
5. よくある質問(FAQ)
Q1.「副作用」や「リスク」は、どのくらい詳しく書けばいいですか?
その施術で一般的に考えうる主なものを、患者が理解できる言葉で網羅的に記載することが求められます。発生頻度や具体的な症状にまで触れることが望ましいですが、まずは厚生労働省が公表している「医療広告ガイドラインに関するQ&A」の事例を参考に、最低限記載すべき項目を網羅することが重要です。
Q2.「〇〇さんの二重、すごく自然で満足!」といった患者様の声を紹介するのはOKですか?
医療機関にとって有利な情報ばかりを集めた体験談は、患者を不当に誘引し、客観的な選択を阻害する可能性があるため、原則として認められていません。専門家への相談を強く推奨します。
Q3. 限定解除の条件は、ウェブサイトの全ページに記載する必要がありますか?
いいえ、全ページに記載する必要はありません。限定解除を適用したい広告(例:ビフォーアフター写真)が掲載されている、そのページ自体で関連する条件をすべて満たしている必要があります。
6. まとめ
- 医療広告ガイドラインは患者を守るためのルールだが、「限定解除」という例外がある。
- 限定解除はウェブサイトなどが対象で、チラシや看板では適用されない。
- 限定解除を適用すれば、ビフォーアフター写真や未承認機器の広告も可能になる。
- そのためには「大前提+4つの必須条件」をすべて満たす必要がある。
- 限定解除は規制の抜け道ではなく、患者への「誠実な情報提供」の証である。
限定解除を正しく活用することは、規制を守るという守りの姿勢だけでなく、患者様からの信頼を獲得し、貴院が選ばれる理由を伝えるための「攻めの武器」にもなり得ます。
しかし、その条件は複雑で、「この表現で本当に大丈夫だろうか…」と判断に迷う場面も少なくないはずです。
厚生労働省のホームページや、医療広告ガイドラインQ&Aなどを見たり、弁護士や医療広告ガイドラインに精通した専門家に相談したりしましょう。
貴院のウェブサイトは、美容医療を検討する患者様に、心から信頼されていますか?
「自院のサイトは大丈夫か不安…」「限定解除の条件を満たせているか見てほしい」
そんなお悩みは、私たち医療広告の専門家にご相談ください。