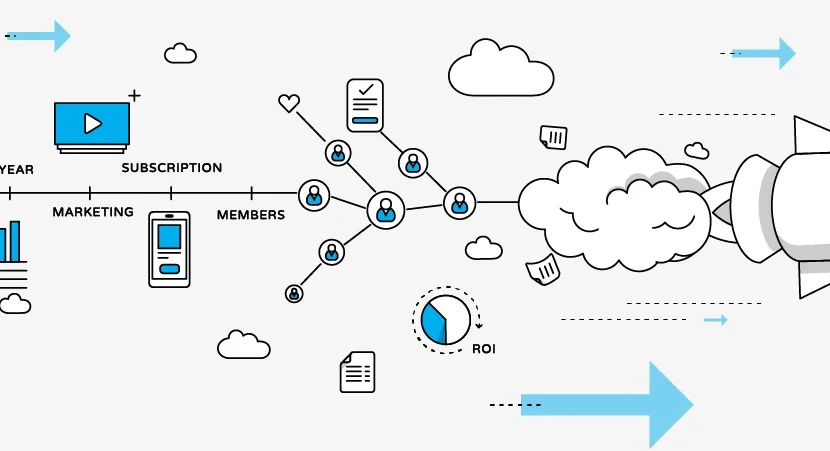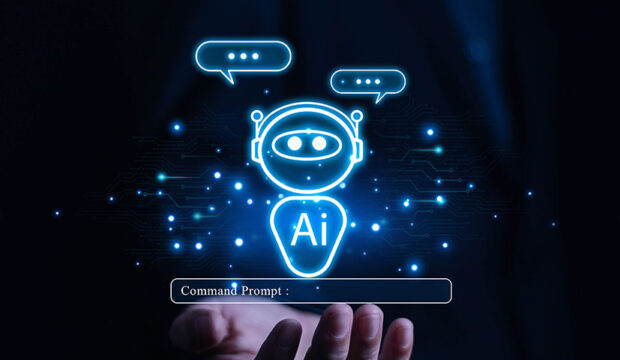「うちのクリニックのホームページ、この表現は大丈夫…?」
「SNSの投稿が、気づかないうちにガイドライン違反になっていたら…」
近年、患者さんが医療情報を得る手段として、ウェブサイトやSNSは不可欠なツールとなりました。しかし、その手軽さの裏側で、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」による規制が年々厳しくなっていることをご存知でしょうか
近年、患者さんが医療情報を得る手段として、クリニックのウェブサイトやSNSの重要性がますます高まっています。しかし、これらのオンライン上の情報発信も「医療広告」として扱われ、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」による規制の対象となることをご存知でしょうか。
2018年の医療法改正により、従来は規制対象外と解釈されることもあった医療機関のウェブサイトも明確に広告規制の対象となりました。これは、特に美容医療サービスに関する消費者トラブルの増加が背景にあります。
このコラムでは、クリニックのウェブサイト運営に携わる担当者の皆様が、複雑な医療広告ガイドラインを正しく理解し、日々の業務でコンプライアンスを確保できるよう、2025年現在の最新情を踏まえ、ポイントを分かりやすく解説していきます。
今回は、「何が医療広告にあたるのか」という基本的な定義と、ウェブサイトやSNSがどのように規制対象となるのか、そして2025年におけるガイドラインの最新動向について詳しく見ていきましょう。
【この記事の目次】
1. 「医療広告」の正しい理解:担当者が押さえるべき2つの要件
医療広告ガイドラインにおいて、「広告」とみなされるかどうかは、以下の2つの要件をいずれも満たすかどうかで判断されます。
要件① 誘引性
患者の受診等を誘引する意図があること。
(例:治療法の紹介、キャンペーン告知)
要件② 特定性
医療機関名や医師名が特定できること。
- 誘引性:患者の受診等を誘引する意図があること
特定の医療機関への受診を促すような内容が含まれている場合、誘引性があると判断されます。例えば、クリニックの治療法を紹介したり、キャンペーン情報を告知したりする内容は、これに該当する可能性が高くなります。 - 特定性:医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名・名称または病院・診療所の名称が特定可能であること
情報発信元であるクリニック名や医師名が明らかである場合、特定性があると判断されます。
この2つの要件を満たすものは、たとえ「広告」と明記していなくても、医療広告ガイドラインの規制対象となります。
2. ホームページやSNSも規制対象!具体的なケースと注意点
医療機関の公式ウェブサイトはもちろんのこと、ブログやSNS(Instagram、Facebook、X(旧Twitter)、LINE公式アカウントなど)における情報発信も、上記の「誘引性」と「特定性」を満たせば医療広告として扱われます。
注意すべき具体的なケース:
- クリニック公式ブログでの治療紹介記事: 新しい治療法や導入した医療機器について解説する記事は、患者の受診を促す意図があると見なされれば広告に該当します。
- SNSでのキャンペーン告知: 「期間限定で〇〇施術割引!」といった投稿は、明確に誘引性があり、広告と判断されます [7]。
- 医師やスタッフ個人のSNSアカウント: 個人のアカウントであっても、その投稿内容が実質的に患者を誘引し、所属する医療機関が特定できるものであれば、医療広告と見なされる可能性があります。例えば、医師が自身の勤務するクリニックでの施術を推奨するような投稿は注意が必要です。
- 患者による体験談の取り扱い: 患者自身が自主的にSNSやブログに投稿する体験談は、原則として医療機関からの誘引性が認められない限り広告には該当しません。しかし、医療機関が患者に投稿を依頼したり、投稿に対して金銭や物品などの便宜を供与したりした場合は、その投稿は「広告」とみなされ、規制の対象となります。
また、医療機関が口コミサイトから自院に有利な体験談を選んでウェブサイトに転載する行為も、広告規制の対象となるだけでなく、誇大広告と判断される可能性があります。
ウェブサイト担当者としては、自院が発信するオンライン上のあらゆる情報について、これらの要件に照らし合わせ、医療広告ガイドラインの規制対象となる可能性を常に意識しておく必要があります。
3. 2025年医療広告ガイドラインの最新動向:オンライン診療の明確化など
医療広告ガイドラインは、医療を取り巻く環境の変化に対応するため、継続的に見直しが行われています。直近では、令和7年(2025年)3月11日に「医療広告ガイドラインに関するQ&A」が改訂されました [2]。
この改訂における主な更新点の一つとして、オンライン診療に関する広告の取り扱いが更新されたことが挙げられます。これは、近年のオンライン診療の普及という医療提供体制の変化を反映したものであり、ウェブサイト上でオンライン診療の案内を行う医療機関にとっては特に重要な変更点と言えるでしょう。
また、厚生労働省が令和7年(2025年)3月に作成した「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第4版)」は、最新の規制動向を踏まえた具体的なNG事例・OK事例を豊富に掲載しており、ウェブサイト担当者が実務上の判断を行う上で必読の資料です。
これらの最新情報を常に確認し、自院のウェブサイトやSNS運用が最新のガイドラインに適合しているかを定期的に見直すことが、コンプライアンスを遵守した適切な情報発信には不可欠です。
4. まとめ
- 「誘引性」と「特定性」の2つの要件を満たすものは、媒体の種類を問わず医療広告として扱われる。
- クリニックの公式ウェブサイトやSNSだけでなく、スタッフ個人の発信や、医療機関が関与した患者の体験談も規制対象となり得る。
- 医療広告ガイドラインは定期的に更新されており、2025年3月にはオンライン診療に関するQ&Aなどが改訂されたため、最新情報のキャッチアップが不可欠。
今回は、医療広告ガイドラインにおける「医療広告」の基本的な定義と、ウェブサイトやSNSがどのように規制対象となるのか、そして2025年における最新動向について解説しました。
次回のコラムでは、ウェブサイトでより多くの情報を合法的に発信するための鍵となる「限定解除」の要件について詳しく解説します。
「厚労省から改善指導の書面が届いた」「どう直せばいいか分からない」など、医療広告ガイドラインに関するお悩みや、ホームページの修正依頼など、専門家のアドバイスが必要な場合は、どうぞお気軽にご相談ください。